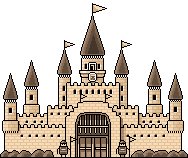<造幣局 桜の通り抜け>
平成28年4月8日(金曜日)から4月14日(木曜日)までの7日間
造幣局の桜は、明治の初めに藤堂藩の蔵屋敷から移植され、品種が多いばかりでなく、
他では見られない珍しい里桜が集められていたので、
明治16年、時の造幣局長(遠藤謹助)の「局員だけの花見ではもったいない。
大阪市民の皆さん方と共に楽しもうではないか。」
との提案により、満開時の数日間、構内川岸の桜並木の一般開放が始まりました。
「通り抜け」という名前は、最初から付けられていた名前ではなく、観桜は一方通行で、
引き返すことが出来ないところから、いつしか、「通り抜け」という名前が定着し、親しまれています。
「通り抜け」は戦争で一時中断されましたが、昭和22年に再開され、昭和26年からは夜桜も始まりました。
現在では浪速の春の風物詩として全国的に有名になり、
各地からの桜見物者で賑わい、期間中の入場者数は約70〜80万人に及んでいます。
   
※久しぶりにリフレッシュできました!
|
 |
旧淀川沿いは、昔から景勝の地で、
春は桜、秋は月見、夏は涼み舟など
四季折々のにぎわいを 見せ、
特に春の桜は有名で、
対岸を桜ノ宮と呼ぶにふさわしく、
この一帯に桜が咲き乱れていたと言われています。
|
 |
平成28年の通り抜けでは、
133品種、349本であり、
その内8割程度が八重桜(里桜)です
 |